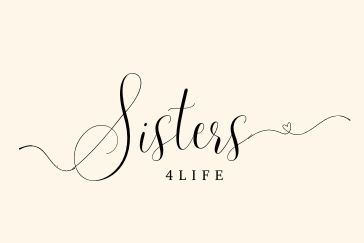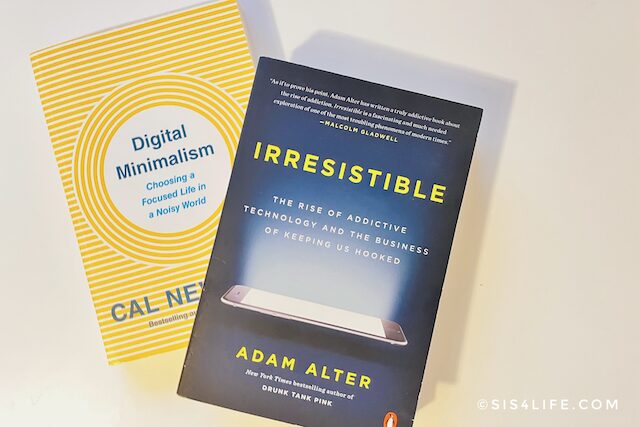誰もがスマホを手に生活する現代。
スマホは便利な反面、知らず知らずのうちに依存に陥るリスクも潜んでいます。
ついスマホをさわってしまう…
気づけばSNSを無意識にひらいている…
そんな抜け出したいのに抜け出せない状態に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、スマホ依存に向き合う手がかりを与えてくれる本を3冊ピックアップしてご紹介します。
- スマホ依存が誰にでも起こりやすい理由
- 実際に参考になったおすすめ本3冊の紹介
スマホ依存は誰にでも起こりうる問題


スマホは私たちの生活に欠かせない存在ですが、その中にはSNSやゲームなどさまざまな誘惑があり、一度ハマってしまうとなかなか手放せなくなるのも現実です。
そのため、スマホ依存は、子供・学生・社会人・主婦・高齢者といった枠を超えて、現代を生きるすべての人が直面しやすい問題となっています。
気づけば「なんとなくSNSを開いてしまう」「寝る前にダラダラと動画を見続けてしまう」など、本人の自覚がないまま依存状態に陥ってしまうことも珍しくありません。
その背景には、スマホをはじめとする現代のデジタルサービスが、私たちを依存させるように設計されていることがあります。
たとえば、SNSの通知や動画アプリのおすすめ機能、ゲームの報酬デザインなど、私たちの注意を引き続ける仕組みはいたるところに組み込まれています。
スマホ依存は意志の弱さではなく、誰もがハマりやすい仕組みの中で起きる自然な反応です。
さらに、
- 友人や家族とのつながりがSNSに依存する
- 仕事の連絡がスマホ中心になる
- 暇つぶしの手軽さから習慣化しやすい
といった現代特有の生活スタイルも、スマホを手放しづらくしている要因です。
だからこそ、「依存しているかも」と感じたら、まずは依存の原因を知り、少しずつ使い方を見直していくことが大切です。
スマホ依存に悩む人におすすめの本3選


「ついスマホさわってしまう…」
「スマホの使用時間を減らしたいのに減らせない…」
そんな葛藤を抱えている方は多いかと思います。
私自身、スマホの使いすぎで悩んでいた時期があり、スマホ依存に関する本を何冊か読んできました。
その中でも特に参考になった3冊を今回はピックアップしてご紹介します。
| おすすめの本 | こんな人におすすめ |
|---|---|
| スマホ脳 | なぜスマホに依存するのかを脳科学的な視点から知りたい人 |
| デジタル・ミニマリスト | 具体的な改善方法を実践したい、デジタル習慣を見直すヒントが欲しい人 |
| 僕らはそれに抵抗できない | 依存症ビジネスの仕組みとその予防策を知りたい人 |
①スマホ脳 ─ スマホ依存の脳科学的な理由を知る
どうして私たちは、スマホに依存してしまうのか
「なぜスマホの通知がなると、チェックせずにはいられないの?」
「なぜ寝る前にスマホをみると睡眠の質が落ちるの?」
そんな疑問を脳科学の視点から解き明かしてくれる本が『スマホ脳(原作:Skärmhjärnan)』です。
著者はスウェーデンの精神科医アンダース・ハンセンさん。
最新の研究データや、人類の進化過程をベースに、どうして私たち人間はスマホに依存してしまうのかをわかりやすく解説してくれる一冊です。
スマホを使う私たちが漠然と感じていたことや普段ついついやってしまいがちな行動が、理論的に説明されているので納得しやすい内容です。
読後は自分の行動を客観視しやすくなるはず
ハンセンさんによると、スマホの使い過ぎは、私たちに次のような悪影響を及ぼすリスクが高くなるようです。
- SNSを使うほど孤独感が増し、人生の満足度が下がる
- ブルーライトが体内時計を狂わせ、睡眠の質を低下させる
- マルチタスクにより記憶力や集中力が低下する
本の最後には、デジタル社会から受ける影響を最小限に抑えるためのアドバイスも紹介されています。
内容は、デジタル社会を生きる私たちのほとんどのが心当たりのあるテーマなので、比較的に読みやすいかと思います。
スマホを全否定するのではなく、客観的な視点から実際に行われてきた数々の研究結果がまとめられているのがよかったです。
紹介されている研究には、デジタルネイティブ世代を対象にしたもの多く紹介されているため、子どもにスマホを持たせている保護者の方にもおすすめです。
ハンセンさんが言うように、私たちがテクノロジーに支配されるのではなく支配する立場であるためには、まずは知識を得ることが大切です。
スマホと上手に付き合うための第一歩に『スマホ脳』を読んで、スマホに依存してしまう理由を脳科学的な視点から理解してみるのはいかがでしょうか?
②デジタル・ミニマリスト ─ 本質的にスマホとの関係を見直す
どうやったらスマホと上手く付き合っていけるのか
「スマホ依存の改善方法を知りたい。」
「スマホの使用を減らす実践的なアプローチが知りたい。」
そんな方におすすめな本が『デジタル・ミニマリスト(原作:Digital Minimalism)』です。
著者は、アメリカのジョージタウン大学でコンピューター科学を専門とする研究者のカル・ニューポートさん。
この本では、デジタル・ライフを根本的に改善する方法として、『Digital Minimalism』というメゾットが紹介されています。
このメゾットのポイントは、完全なデジタル断ちを求めるのではなく、自分にとって価値のあるツールを取捨選択すること!
「デジタル片付け」で、不要なデジタルツールやオンライン活動を取り除いて、その時間を、趣味や自分と向き合うことに費やし、人生の質をあげようという考え方です。
- SNSの利用を目的ごとに見直す
- なんとなく続けていたアプリの削除
- デジタルから離れて得た時間を、趣味・学び・人とのつながりへ再投資する
といった具合に、習慣レベルからデジタルライフを再構築していきます。
本の中では、「デジタル・ミニマリズム」の具体的な方法と共に、2017年末に1600人を対象に行われたデジタル片付け実験の結果も多数記載されています。
その実例から、理論だけでなく「実際に効果があった方法」を知れるのも魅力です。
「さすがにそこまではできないかも‥」
というアドバイスも一部ありますが、全てを実行に移すのではなく、大切なのは自分に合う部分だけを取り入れること。
本の内容は、極端なスマホ断ちを推奨するものではなく、「自分にとって価値のあるテクノロジーだけを選ぶ」という実践的で現実的なアプローチが中心になっているのがよかったです。
デジタル・ライフを改善するヒントがぎゅっと詰まった一冊なので、具体的な改善方法が知りたい方は参考にしてみてはいかがでしょうか?
③僕らはそれに抵抗できない ─ 依存症ビジネスの裏側を知る
依存症ビジネスはどうやってつくられるのか
「気づけば一日中ゲームに没頭していた…」
「Netflixでドラマを徹夜でイッキ見してしまった…」
といった現代人を蝕んでいる依存症。
これまで、依存症と言えば、アルコールやドラッグなど「モノ」に対する依存を表すことがほとんどでした。
しかし現代では、SNS・ゲーム・動画サービスが「やめられない」といった、行動そのものに依存するケースが急増しています。
その背景にあるのが、企業がユーザーを依存させるために設計した「依存症ビジネス」です。
そんなデジタル社会での「依存症」と「依存症ビジネス」の理解を深めるのにおすすめな本が『僕らはそれに抵抗できない-「依存症ビジネス」のつくられかた(原作:Irresistible)』です。
企業がどのように私たちの心理を分析し、「もっと見たい」「もっと遊びたい」と思わせる仕組みを作っているのかを解説してくれる一冊になっています。
この本を読むことで、依存してしまうのは「意志が弱いから」という訳ではなく、依存するように巧妙に仕掛けられた罠があるからということに気づけます。
ゲーム依存についての記述も豊富で、子どもがゲームやスマホに夢中になってしまう理由を心理とデザインの両面から学べるので、親世代にとっても「どんなポイントに気をつけて見守ればいいのか」を理解する助けになるかと思います。
本の中では、私たちユーザーを依存に陥れる6つのテクニックと、依存症に立ち向かうための具体的なヒントがまとめられています。
SNS・ゲーム・動画サービスが、なかなかやめられないと感じている方は、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか?
まとめ
現代を生きる私たちは、誰もがスマホ依存に陥る可能性を抱えています。
その背景にある「脳の仕組み」や「企業が仕掛ける罠」、その対策のヒントを知っているか、そうでないかで今後スマホとの付き合い方も大きく変わってくるかと思います。
この記事で紹介した3冊は、それぞれ違った角度からスマホ依存を理解し、改善のヒントを与えてくれる本です。
1日10分間、スマホを置いて、その時間を読書にあてるだけで、違った視点が見えてくるはずです。
これからのデジタル社会を、使われる側ではなく、使いこなす側として生きるためにも、まずは一冊手に取ってみてはいかがでしょうか


三女
一児のママ(息子)
IT系専門職に就いていて、このブログの主な運営者です。